はじめに:申請が通った日のこと
こんにちは。
この記事では、私がうつ病で障害厚生年金2級を自力で申請し、実際に通過した体験を正直に綴っています。
最初にお伝えしたいのは、申請結果が届いたときの気持ちです。
2023年12月、障害年金の支給決定通知が届きました。
その瞬間、私は泣きました。
「まだ生きていてもいいのかもしれない」
それが、通知を見たときに湧いてきた正直な気持ちでした。
正直、それまでは
「もし落ちたら、もう終わりにしようかと思ってた」
そんなふうに思ってしまうくらい、不安定な時期でした。
それでも、なんとか調べて、書類を書いて、申請をして…。
不安や涙や絶望の中で、手を動かし続けました。
そして、「あなたは支給対象です」と言われたことで、ほんの少し、自分の存在が認められたような気がしたのです。
障害年金の申請は、ただの「制度の手続き」ではありません。
心がボロボロの状態で、自分の弱さを全部さらけ出さなければならない、とても過酷な作業です。
でも私は、街角の年金相談センターという場所を利用し、自分の力で2級を受理してもらうことができました。
「本当に通るの?」「どうやって進めればいいの?」
「申立書ってどう書くの?」「主治医になんて言えば…?」
私も全部、悩みながら一歩ずつ進みました。
次からは、なぜ障害年金を申請しようと思ったのか、その理由や背景についてお話しします。
障害年金の申請を決めたのは、仕事を退職した直後のことでした。
なぜ障害年金を申請したのか
私はそれまで「傷病手当金」をもらいながら休職しており、主治医も「復職を目指しましょう」という方針でした。
そのため、当初は障害年金のことは全く考えていませんでした。
でも、傷病手当金が終わり、少しだけ職場に復帰してみたものの、体調が戻らず、再び症状が悪化。
そのまま退職することになりました。
退職の話を主治医に伝えたとき、こう言われました。
「それなら、障害年金を申請しましょう」
正直そのときは、心も体も限界で、言われるがままという感じでした。
でも、その言葉がなかったら、今も制度の存在すら知らず、何の支援もないまま苦しんでいたと思います。
申請を決めた理由は、シンプルに言うと「生きるためのお金が必要だったから」です。
「いただけるものはいただきます」――当時はそんな気持ちでした。
心の中では、
「こんな状態でも、制度に頼っていいの?」
「本当に自分が該当するのかな…?」
と、罪悪感や戸惑いもたくさんありました。
でも今は思います。
生活の不安を少しでも軽くして、治療に専念するために、障害年金は必要な制度だったのです。
申請までのスケジュールと流れ
私が障害年金の申請を始めたのは、退職した直後の9月中旬。
金が全てではないけど、すべてには金が必要。
そして、支給決定通知が届いたのが12月上旬でした。
申請からわずか3ヶ月。
これはかなり早いほうだと思います。
普通は、年金事務所の予約を取るだけでも1ヶ月先になることが多く、申請完了までに数ヶ月かかるケースが多いと聞きました。
利用したのは「街角の年金相談センター」
私がスムーズに申請を進められた理由のひとつは、街角の年金相談センターを利用したことです。
ここは、年金事務所とほぼ同じ機能をもつ相談窓口で、
- 予約不要(予約も可)
- 書類の配布・確認・提出が可能
- 丁寧な対応(←とてもありがたかった…!)
私はこのセンターを3回ほど利用しました。
- 必要書類をもらう(診断書用紙、申請書、申立書など)
- 書類の記入ができたら、提出に行く
- 書き間違いの指摘を受け、その場で書き直し、再提出
そのたびに、職員の方が本当に丁寧に見てくれて、
「大丈夫ですよ、ここだけ直せば完璧です」と優しく教えてくれました。
実際のスケジュール(私の場合)
- 8月末:退職
- 9月中旬:申請準備開始(書類集め)
- 10月上旬:主治医に診断書を依頼(約1ヶ月)
- 11月上旬:書類完成・提出
- 12月初旬:支給決定通知が届く
申請までの工程は人によって違いますが、
「自分の状態に合った進め方を選ぶ」ことで、無理なく乗り越えることができました。
書類作成の苦労と工夫
障害年金の申請で、**一番つらかったのが「書類を書くこと」でした。
特に、「病歴・就労状況等申立書」**という書類は、私にとって心身ともにかなり負担の大きい作業でした。
自分の弱さを書くことが、想像以上につらい
申立書には、「過去にどんな症状があって、どんなことができなくなったか」を時系列で詳しく書いていきます。
- どの時期に何の症状が出たか
- 働いていたとき、何ができなくなったか
- 日常生活で制限されていることは何か
…など、「自分ができないこと」を正直に書く必要があります。
それが本当につらかった。
心の中では「自分はまだ大丈夫」と思いたいのに、それを否定するような作業です。
「ここまでできない」と正直に書くことに、最初は抵抗がありました。
書いている途中で発作が起きたことも
過去の自分を振り返ること、できなくなったことをひとつひとつ思い出すこと――
そのたびに、涙が出たり、呼吸が乱れたり、パニック発作のような症状が出ることもありました。
私は5年以上、毎日少しずつ日記をつけていたので、それを参考にできたのが救いでした。
診察のときに言葉が出なくて、ノートに気持ちを書いて渡していた時期もあり、その記録が本当に役立ちました。
通院記録や日記に使っていたノート
医師とのやり取りを整理するのにとても助かりました。
▶ Amazonで見る
工夫したこと:時系列+シンプルに「できないこと」を伝える
私が工夫したポイントは:
- 時系列で文章にまとめる(いつ何が起きたか)
- 「〜ができない」「〜の補助が必要」とハッキリ書く
- できることも、**「声かけが必要」「条件付きでできる」**と明確に書く
例)
・「入浴は一人でできるが、気力がない日は家族に声かけされてようやく動く」
・「公共交通機関は発作が出るため利用できず、通院は家族の送迎」
街角年金相談センターでのアドバイスが心強かった
書類を書いたあと、街角の年金相談センターで内容を見てもらったとき、
担当の方がこう言ってくれました。
「これ、本当は誰か第三者が書いてもおかしくないくらい、大変な内容ですね…」
その瞬間、胸にあったものがふっとゆるんで、涙が出そうになりました。
パワハラやセクハラ、家庭環境のこと――誰にも話せなかったことを、やっと「わかってもらえた」と感じたんです。
申請の書類づくりは、心が元気なときでさえ大変です。
うつ病の最中にやるには、正直“命を削る”くらいの覚悟が必要でした。
でも、それをやりきったことが、支給決定につながったのだと思います。
主治医とのやり取り
障害年金の申請で、もう一つ大きなハードルになるのが「主治医とのやり取り」です。
特に診断書の依頼は、医師の協力なしには絶対に通れない道です。
申請のきっかけは、主治医のひとこと
私の場合はとても恵まれていて、退職することを伝えたとき、主治医の方からこう言ってくれました。
「じゃあ、障害年金を申請しましょう」
私はそのとき、正直なところ意識もぼんやりしていて、制度の詳細もわからない状態でした。
でも、先生のそのひとことがなければ、申請しようとも思えなかったと思います。
診断書は1ヶ月ほどで完成
診断書の依頼から完成までは、約1ヶ月。
主治医は私の症状を長く診てきてくださっていたので、内容もスムーズに書いていただけました。
中には、診断書を書いてもらえない/受け取るまでに数ヶ月かかる/内容が合っていなくて申請が通らない…という話もよく聞きます。
私は幸運にも、しっかり協力してくれる先生に出会えていたのだと思います。
主治医との関係づくりも大切
私は、診察中にうまく話せないときのために、ノートに気持ちを書いて渡していました。
また、過去の症状や困っていたことをメモにして、あらかじめ先生に渡していたこともあります。
その積み重ねが、きっと診断書の内容にも反映されたのだと思います。
診断書は、ただ「医師が書くだけ」のものではなく、患者との信頼関係があってこそだと実感しました。
提出と支給決定までの流れ
すべての書類が揃ったあと、私は街角の年金相談センターに再び足を運び、申請を提出しました。
診断書・申請書・病歴就労状況等申立書の3点をそろえたうえで、担当の方に確認してもらいました。
提出に必要だったもの(私の場合)
- 障害年金請求書(年金申請書)
- 病歴・就労状況等申立書
- 診断書(障害認定日から1年以内だったので1枚)
- 年金手帳(基礎年金番号確認のため)
- 通帳(振込口座)
- 印鑑(書類訂正のため)
- 住民票(役所で取得)
※このとき、障害年金生活者支援給付金の申請書類も、その場で説明を受けて一緒に提出しました。
担当者の対応が温かかった
相談センターの担当の方は、こちらの状況にとても寄り添ってくれる方で、
「この申立書、本当にご本人が書いたんですか…?大変でしたね」
と一言かけてくれました。
長年パワハラや家庭のことで悩んできたことを、やっと「わかってもらえた」と感じたんです。
提出から結果通知までの流れ
- 11月上旬:書類提出
- 12月初旬:結果通知(支給決定)
その瞬間、胸にあったものがふっとゆるんで、涙が出そうになりました。
たったの1ヶ月。これはかなり早いほうだと思います。
私は「不備があったらどうしよう」「返却されたらどうしよう」と、毎日不安でたまりませんでした。
それでも、3ヶ月以内に結果が出たことで、精神的にもようやく一区切りつけることができました。
支給決定とあわせて申請した制度
▶ 障害年金生活者支援給付金
これは、一定の所得条件を満たした障害年金受給者に支給される制度で、申請しないともらえません。
私は相談員の方がその場で説明してくれて、提出することができました。
結果が届いたときの気持ちは、**「ようやく生きていてもいいと思えた」**というものでした。
ここまでの道のりは本当に大変でしたが、次は「自力申請できた理由」や、できないときの選択肢について書いていきます。
自力申請できた理由と、できないときの選択肢
私は今回、社労士などの専門家に頼らず、完全に自力で障害年金の申請を行いました。
でもそれは、たまたま「条件がそろっていたから」できたことだと、今振り返って思います。
私が自力申請できた理由
- 初診からずっと同じ病院に通っていた
- 主治医が協力的で、診断書を早く書いてくれた
- 障害認定日から1年以内だったため、診断書が1枚で済んだ
- 付き添い(親)がいたことで外出・役所対応ができた
- 街角の年金相談センターを利用できた(予約不要・相談可能)
これらがすべて揃っていたからこそ、精神的にもギリギリの状態の中、なんとか申請を完了することができたのです。
申請は「一人でやるのが当然」ではない
障害年金の申請は、正直いってうつ病の人が自力でやるには過酷すぎる作業です。
頭が回らない、集中できない、体が動かない、役所の雰囲気がつらい――そのすべてがハードルになります。
だからこそ、「自分には無理かも」と思ったら、早めに第三者の力を借りてほしいと本気で思っています。
第三者に頼る選択肢
- 社労士に依頼する(有料だが、書類や提出まで代行してくれる)
- 自治体の障害者支援窓口に相談する(ケースワーカーが助言してくれる場合あり)
- 医療機関内の心理士やソーシャルワーカーに相談する
- 家族や信頼できる友人に同行・代筆をお願いする
金銭的に難しいと感じる人も多いと思います。
でも、精神的・身体的なダメージを考えると、「お金を払ってでもサポートを受けた方がいい」ケースも多いです。
私は、復職経験があったことや、親の助けがあったことでなんとか申請までこぎつけました。
でも、そうでなければ、間違いなく社労士を探していたと思います。
「障害年金は、必要な人が受け取るべきもの」
そう思えるようになるまで、時間がかかりました。
申請を迷っている方も、どうかひとりで抱えこまず、**「制度を使ってもいい」**という気持ちを、少しずつ育てていってほしいです。
保険の無料相談サイト「ガーデン」おわりに:お金は命の土台
障害年金の申請が通ったことで、私はようやく「生きていてもいい」と思えるようになりました。
実際に支給が始まった今でも、その気持ちは変わりません。
障害年金だけで生活が豊かになるわけではありません。
でも、「生活の不安が少しでも軽くなる」ということが、回復の大きな一歩になるのだと、私は身をもって知りました。
以前どこかで見た言葉があります。
金がすべてではないけど、すべてには金が必要。
この言葉が、心にずっと残っています。
治療費、通院交通費、薬代、保険適用外のカウンセリング――
病気と向き合いながら生活していくには、想像以上にお金がかかります。
私は、年金を受け取ることに罪悪感を持っていた時期もありました。
「こんな自分がもらっていいのかな」
「働かずにお金をもらうなんて…」
でも今は、こう思います。
今までまじめに保険料を納めてきたからこそ、
必要なときに、制度を使う権利がある。
障害年金の申請は、心も体も弱っている人が、自分の傷をひとつひとつ振り返り、書き起こすという、過酷な作業です。
でもそれを乗り越えたからこそ、私は今、生きてここにいます。
もし、今この記事を読んでいるあなたが、
「申請したいけど、自分なんかが通るのかな」
「もう疲れてしまって、何もしたくない」
そんな気持ちでいたとしても、大丈夫です。
あなたにも、支援を受ける権利があります。
少しでも、今日を生きる力になりますように。
私の申請体験が、ほんの少しでもあなたの支えになれたら嬉しいです。
あわせて読みたい
▶︎ note|障害年金申請中に感じていた正直な気持ちを綴った記録はこちら
ブログでは手続きや流れをまとめましたが、
noteでは、申請中の不安や葛藤、待っていた時間の気持ちをそのまま言葉にしています。
「同じような気持ちを抱えている方に、少しでも届いたら」と思って書きました。
また、病歴申立書の書き方や、診断書の補足、入院中の体験なども今後記事にしていく予定です。
よければそちらもご覧ください。
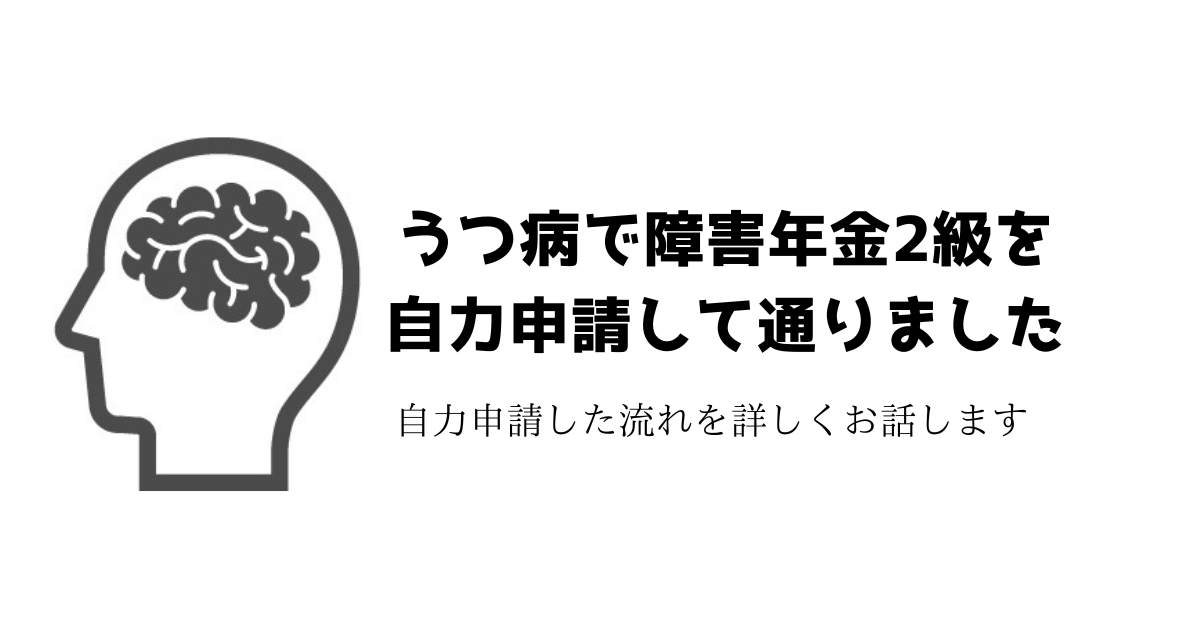


コメント